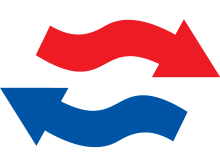仕事柄イーサネットについて熟知している必要があり、教科書を揃えていたので復習ついでにメモ。
詳細までは書かない。
いずれの本もPoE(IEEE802.3af)や認証(IEEE802.1X)等はまだ無い時代のものなのでその辺は割り引く必要がある。
発行年月日順。
*はお勧めマーク(*** > ** > * > (null))。
-----------------------------------------

「ギガビットイーサネット徹底解説」
(Data Communications Gigabit Ethernet Handbook)
Stephen Saunders編
井早優子訳 / 林田朋之、米沢寿員監訳
日経BP社
1999年10月25日 1版1刷 (原本は1998年発行)
4200円
[メモ]
章ごとに執筆者が異なるという構成。イーサネットも細かく見れば分野は広いのでその道の専門家に書かせる趣向。27章を27人と編集スタッフで分担している。複数の章を担当している人もいれば、一つの章を複数で担当している場合もあり、執筆者が競合メーカ同士だったりすので、中立性を保つために編集スタッフが記述しているところもある。職場でも同僚達と分担すればそれなりの本を作れそうだ。編者はおいしいというか(バランス取りに苦労したであろうか、章毎の違和感はあまり感じない)。
内容に目を移すと、タイトル通りギガビットイーサネットにフォーカスした本。
どちらかというと、ファーストイーサネット中心のネットワークを管理している人に対してギガビットイーサネットへの移行にあたって注意配慮すべき点が書かれており、また、ATMやCSMA/CD(半二重通信)に気を遣っているように、まさにギガイーサネット登場の過渡期に出版された本。
また、"10BaseT"とか正規でない書き方で統一されている(正式には"10BASE-T")
というところも含め、現在では購入する理由はあまりない。
-----------------------------------------

「詳説 イーサネット」 *
(Ethernet - The Definitive Guide -)
Charles E. Spurgeon著
柏木由美子訳/櫻井豊監訳
オライリージャパン
2000年12月20日 初版第1刷 (原本は2000年発行)
4200円
[メモ]
挿入されている図が適切で理解を助けるのに役立つ。
「5章自動ネゴシエーション」は詳しい。
「15章ツイストペアケーブルとコネクタ」は電話からの関連性の記述がいくつかあり、また、感電の危険性があることに対する注意喚起が行われているのはこの本だけ。
全体的にいわゆる教科書的でさらっと流れてしまうのはいわゆるオライリー本っぽい。
講義を聴いているようだ。
-----------------------------------------

「高速Ethernetの理論と実装」 **
(Switched, Fast, and Gigabit Ethernet, Third Edition)
Robert Breyer/Sean Riley著
イデア コラボレーションズ訳
アスキー
2001年4月1日 初版 (原本は1998年12月21日発行)
4200円
[メモ]
「第6章ケーブル配線と物理層の詳細」「第8章構成部品」が他にはないトピックがあるように物理層の説明が細かい。
「第1章Ethernetの歴史」も「1.1 Ethernetの起源:ALOHA無線システム(1968~1972」から始まり「1.2 Xerox PARCでの最初のEthernetの構築(1972~1977)」「1.3 DEC, Intel, およびXeroxによるEthernetの標準化(1979~1983)」「1.4 3ComによるEthernetの製品化(1980~1982)」と続き、「1.5 StarLAN:低速、しかし偉大なアイディア(1984~1987)」などもあって「1.11 Gigabit Ethernet(1995~1998)」まで締めるまで同様におもしろい。
この本にも「LANスイッチング徹底解説」同様、命名規則が載っている。
ただ、オートネゴシエーションについて、片端がオートネゴシエーションでもう片端が固定の場合、速度については優先順位に則って自動で調整されるが、通信モードが半二重となることはこの本からでは読み取れない(p.116/3.6 IEEEの自動ネゴシエーション標準規格)。(これで痛い目に遭ったことがある)
「第1章Ethernetの歴史」「第6章ケーブル配線と物理層の詳細」「第8章構成部品」に他の本にはない価値を認める人向け。
-----------------------------------------

「LANスイッチング徹底解説」 **
(The Switch Book - The Complete Guide to LAN Switching Technolgy -)
Rich Seifert著
間宮あきら訳
日経BP社
2001年8月6日 1版1刷 (原本は2000年発行)
4800円
[メモ]
全体にユーモアとエスプリが効いていて、内容も細かく、個人的には一番好き。イーサネットを理解した気になる(スイッチにフォーカスしたタイトルになっていますが)。
商売のツールとしてイーサネットを捉える人(私のような)には後述する「10ギガビットEthernet教科書」が実践的ではある。
「リンクの不変性」(フレームの重複の禁止/配送順序の維持)といった基本中の基本について明記(p.70/p.222)しているのはこの本だけ。
実装方法の命名法もちゃんと記述している(p.28/例:10BASE-Tは正解、10BaseTは間違い→BASEは大文字、読みにくい場合は"-"でつなぐ)。
想定されている前提条件に言及しているのも特記できる。例えば、STPは新しいトポロジーに収束するより早くネットワークが変更されないことを前提としている(p.200)。
ユーモアというのは「5.1.2 ループの回避」では、ループを解決するにはそもそもループとならないような構成にすべきということを暗喩した本文外のショートコメントで(p.190)
患者:「先生、こうすると痛いんですが」 先生:「じゃ、そうしないでください」
と出した後、ループ問題を解決する方法(STP)と詳細について述べた後「5.3.3 独自のループ解決アルゴリズム」で再度(p.217)
(省略)……いまでも通用する金言
と提示してたりする。これ、家でも子どもたちに使っている。
同様に
「全二重型イーサネット」
CSがなく、MAもなく、CDも行わないCSMA/CD
とか(p.289)。イーサネットを定義するIEEE802.3はCSMA/CDを使った通信方式のLANにおけるMACと物理層に関する標準を指すので全二重型通信は自己矛盾であることを面白く皮肉っている。制定当時は半二重しかなかったので互換性維持のためCSMA/CDは1ギガビットイーサネットまで生き続けている。でもその矛盾を取り込みつつ増殖しているのがイーサネットの強みでもあるが、とうとう10ギガビットイーサネットではCSMA/CDは非対応になった。
こういうメタが随所にちりばめられているので凡庸な教科書だとさらっと流してしまうところを記憶にとどめさせてくれる。
守備範囲はIEEE標準、IEEE802.3、IEEE802.3ad(リンクアグリゲーション)、IEEE802.1D(STP)、IEEE802.1Q(VLAN)、ループの解決、スイッチの動作、全二重型通信、CoSとQoSなど。
-----------------------------------------

「10ギガビットEthernet教科書」 ***
石田修、瀬戸康一郎監修
IDGジャパン
2002年4月20日 初版
4000円 (某社より仕事先へ献本)
[メモ]
「ギガビットイーサネット徹底解説」と同様に各章を複数の執筆者が担当する構成。異なるのは、監修者も多くの章を執筆していること。
とりあえずここに書いていることを把握していれば仕事は出来る。
「第10章MAN/WAN/SANへと拡大する最新ethernetの応用例」のWAN/MANの接続構成などが実践的。
広域EthernetサービスやFTTHに関する記述も見られるのも国産本かつ(この中では)最新本であるが故か。
冗長化技術も詳しい。
付録ではあるが各種符号化に関する説明も種類も多く一番詳しい。
特に10Gに特化しているわけではなく、Ethernet全般と周辺技術にまで手を広めている。
とりあえず1冊だけ選べと言われたらこの1冊になる。
-----------------------------------------
通信を生業としている人にとって仕事上で使えるとりあえずの知識としてのイーサネットを吸収したいなら「10ギガビットEthernet教科書」、イーサネットについてもっと知識を深めたいなら「LANスイッチング徹底解説」がお勧め。
こう復習してみると同じイーサネットを題材にしても扱う分野の広さ、専門的深さ、伝える工夫が教科書によって大分違う。
イーサネットの基本を勉強、習得するにはこういった「教科書による学習」の他に「IEEE標準の確認」「実機を用いた実習」「測定器による検証」などがあると思う。
私のPCの裏にささっているUTPケーブルは簡単に接続できてリンクアップを示すLEDが点灯するのを確認する程度でイーサネットに関しては意識もしないし、ほとんど何のノウハウもいらない。最近ではオートMDI/MDI-X機能によりクロスケーブルと知らずに接続してつながらないなどのトラブルを起こすこともなくなった。UTPケーブルも材料と工具があれば簡単に自作できる。
イーサネットは枯れた技術であると見ることも出来る。当面の間、OSI階層モデルでいうレイヤー2(データリンク層)における通信方式はイーサネットの独壇場であるに違いない。
ただ、仕事で用いるイーサネットは大量に/安全に/堅牢にする必要があり、その展開には基本を押さえた上で別の技術が必要であるのだけれど、今はまだ書けないなぁ。